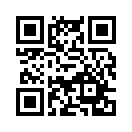2008年12月14日
2008年11月22日
西清寺の銀杏
鳥栖の田代上町
浄土宗
紫友山
西清寺 さいせいじ

2007年9月15日の夕刻
落雷の被害にあった大銀杏
倒壊のおそれがあったため
枝が落とされ、木の上部は
切断されました
2008年秋
何とか 生きています

西清寺のいちょう
鳥栖市の天然記念物
勝尾城の城主
筑紫鎮恒(後の広門)は
天正2年(1574年)に
このお寺の名前を
西圓寺から
西清寺に改めました
この大いちょうは
天正年間(1573年から1591年)に
側室の病気が治ることを祈願し
植えられたもの

自然の力
雷が落ちても
負けないぞ
西清寺の場所は、こちら 続きを読む
浄土宗
紫友山
西清寺 さいせいじ
2007年9月15日の夕刻
落雷の被害にあった大銀杏
倒壊のおそれがあったため
枝が落とされ、木の上部は
切断されました
2008年秋
何とか 生きています
西清寺のいちょう
鳥栖市の天然記念物
勝尾城の城主
筑紫鎮恒(後の広門)は
天正2年(1574年)に
このお寺の名前を
西圓寺から
西清寺に改めました
この大いちょうは
天正年間(1573年から1591年)に
側室の病気が治ることを祈願し
植えられたもの
自然の力
雷が落ちても
負けないぞ
西清寺の場所は、こちら 続きを読む
2008年11月21日
2008年11月02日
長崎街道番所川
鳥栖の長崎街道を歩いていると
こちらの境橋に出あいます。

この川は対馬宋藩と肥前鍋島藩の藩境
川の名前は、轟木川
通称、番所川
肥前鍋島藩の東端、轟木宿の番所が
すぐ近くにあったため、番所川という
名前がついたそうです。
轟木番所

番所には常に侍1人、足軽9人が詰めており
藩内に出入りする人間と荷物を厳重に
調べていたそうです。
轟木日子神社は
すぐ近く
こちらの境橋に出あいます。
この川は対馬宋藩と肥前鍋島藩の藩境
川の名前は、轟木川
通称、番所川
肥前鍋島藩の東端、轟木宿の番所が
すぐ近くにあったため、番所川という
名前がついたそうです。
轟木番所
番所には常に侍1人、足軽9人が詰めており
藩内に出入りする人間と荷物を厳重に
調べていたそうです。
轟木日子神社は
すぐ近く
2008年11月02日
2008年11月01日
長崎街道瓜生野町
鳥栖の本町八坂神社

長崎街道まつり
温かいほうじ茶のおもてなしを受けました。
瓜生野町は田代宿と轟木宿のほぼ中間
現在の本町、秋葉町のあたりなんですね。
瓜生野のえびすさん

古賀書店さんでは、おにぎりやバナナが
無料でふるまわれていました。
長崎街道まつりの総合案内所は
立派な旧家
お座敷にあがって、お抹茶と
水田屋さんの宿場まんじゅうを頂きました。
無料とは、かたじけなく
お仏壇に100円玉を
総合案内所を出て
お菓子の水田屋さんを過ぎ
小さい前川を越えたら、すぐ
現在は秋葉町
旧家が残る町並み


対馬藩宗家の家紋
四目結
昔、造り酒屋さん

昔、油屋さん

こちらでは素晴らしい石庭を拝見できました。
石庭の背景に、マンション
ラバーコーンが置いてあるのは
ご愛嬌
長崎街道まつり
温かいほうじ茶のおもてなしを受けました。
瓜生野町は田代宿と轟木宿のほぼ中間
現在の本町、秋葉町のあたりなんですね。
瓜生野のえびすさん
古賀書店さんでは、おにぎりやバナナが
無料でふるまわれていました。
長崎街道まつりの総合案内所は
立派な旧家
お座敷にあがって、お抹茶と
水田屋さんの宿場まんじゅうを頂きました。
無料とは、かたじけなく
お仏壇に100円玉を
総合案内所を出て
お菓子の水田屋さんを過ぎ
小さい前川を越えたら、すぐ
現在は秋葉町
旧家が残る町並み
対馬藩宗家の家紋
四目結
昔、造り酒屋さん
昔、油屋さん
こちらでは素晴らしい石庭を拝見できました。
石庭の背景に、マンション
ラバーコーンが置いてあるのは
ご愛嬌
2008年11月01日
田代外町天満神社
田代外町の天満神社

神社の由緒書きによれば、
安永8年(1779年)8月18日に
この地の所有者の方が畑を耕していたところ、
菅原道真公の霊像が出てきたそうです。
代官所の許可を得て、この地に社殿を建て
菅公の霊像を本尊とし安置したことが
外町天満神社の起こり
鳥居の年号と楠の樹齢とも
年代が一致するそうです。
鳥栖の長崎街道まつりでは、
こちらの神社でとれた梅を使った
おいしい梅干を頂きました。
田代外町のえびすさん

スタンプラリーのスタンプが置いてありました。
5円玉を置いてきましたよ。
田代外町の追分石


追分石は、享和2年(1802年)以前に建立されたもの
右-さか
左-くるめ道
と彫られています。
田代宿を出発し、肥前鍋島藩の轟木宿を
目指す旅人は右の道を通ります。
大木川を越えて
三角屋村(みすみやむら)

このあたりは、平安時代中頃の天満宮所領
鳥栖庄から続く鳥栖村の北の端
現在の本鳥栖町
長崎街道は、この角を西に曲がります。
こちらの左手には菅原道真公ゆかりの
水影神社があります。
古野町の道しるべ

古野町の角を南に曲がると
瓜生野本町
現在の本町へ
南に曲がってすぐの
古野町の道しるべ

神社の由緒書きによれば、
安永8年(1779年)8月18日に
この地の所有者の方が畑を耕していたところ、
菅原道真公の霊像が出てきたそうです。
代官所の許可を得て、この地に社殿を建て
菅公の霊像を本尊とし安置したことが
外町天満神社の起こり
鳥居の年号と楠の樹齢とも
年代が一致するそうです。
鳥栖の長崎街道まつりでは、
こちらの神社でとれた梅を使った
おいしい梅干を頂きました。
田代外町のえびすさん
スタンプラリーのスタンプが置いてありました。
5円玉を置いてきましたよ。
田代外町の追分石
追分石は、享和2年(1802年)以前に建立されたもの
右-さか
左-くるめ道
と彫られています。
田代宿を出発し、肥前鍋島藩の轟木宿を
目指す旅人は右の道を通ります。
大木川を越えて
三角屋村(みすみやむら)
このあたりは、平安時代中頃の天満宮所領
鳥栖庄から続く鳥栖村の北の端
現在の本鳥栖町
長崎街道は、この角を西に曲がります。
こちらの左手には菅原道真公ゆかりの
水影神社があります。
古野町の道しるべ
古野町の角を南に曲がると
瓜生野本町
現在の本町へ
南に曲がってすぐの
古野町の道しるべ
2008年10月31日
田代八坂神社
鳥栖の長崎街道
田代宿

田代は
対馬藩基肄養父領の代官所が
置かれていた町
昌元寺町、新町、上町、下町、外町の5町で
成り立っていました。
日田道と久留米道と
分岐する交通の要衝
田代八坂神社

長崎街道まつりの午前中の催し物がちょうど終わったころ
和服姿の方がたくさんいらっしゃって、江戸時代の雰囲気が
出ていましたよ。
昌元寺

田代宿から、肥前鍋島藩の轟木宿を目指して
町のお宝を見ながら、のんびり歩きました。
続きを読む
田代宿
田代は
対馬藩基肄養父領の代官所が
置かれていた町
昌元寺町、新町、上町、下町、外町の5町で
成り立っていました。
日田道と久留米道と
分岐する交通の要衝
田代八坂神社
長崎街道まつりの午前中の催し物がちょうど終わったころ
和服姿の方がたくさんいらっしゃって、江戸時代の雰囲気が
出ていましたよ。
昌元寺
田代宿から、肥前鍋島藩の轟木宿を目指して
町のお宝を見ながら、のんびり歩きました。
続きを読む
2008年10月18日
第7回長崎街道まつり
鳥栖の長崎街道まつり
2008年10月26日 日曜日
午前10時から 午後3時まで
開催されます。
田代宿から 轟木宿まで
約5キロの長崎街道
ゆっくり歩いてみたいと
思っています。
街道沿いの見どころ
田代八坂神社、鳥栖八坂神社
秋葉神社、轟木日子神社
秋葉町の旧家
追分石、えびすさん
街道沿いのお菓子屋さん
佐藤製菓本舗さん、水田屋さん
催し物もいろいろ!
写真コンテスト
吟行
スタンプラリー
田代藩札の発行
富くじ
飛び入り歓迎の芸能舞台
The 7th Nagasaki Kaido Festival
will be held in Tosu city, Saga, Japan
on October 26th in 2008.
2008年09月19日
菅原道真史跡
鳥栖にある菅公史跡
姿見の池と腰掛石

菅原道真(845年-903年)の伝説
長崎市の中島天満宮に残っている
聖廟記によると
延喜元年(901年)
菅原道真が大宰府に流されたとき
従った三澄左近将監時遠は
年老いて
瓜生野(現在の鳥栖市元町)付近に隠居
時遠は子どもがいなかったため
道真の五子、長寿麿を養子に
もらったそうです。
道真は、長寿麿に会うため
しばしば瓜生野を訪れ
そのとき、腰をおろしたのが
腰掛の石
長寿麿に与えるため
水に映した自分の顔を描いたのが
姿見の池

石碑

鳥栖駅から轟木町の日子神社を目指して
歩いていくと、途中にあります。
JRの高架橋をくぐって、すぐ左
駐車場はないので、
歩いて行きましょう。
線路沿いに歩いていくのも楽しいし
商店街をのんびり歩くのも良いですね。
せっかくなので
長崎街道を、ちょっとだけ
たどってみるのも良いかも
秋葉町の昔の町並みを見ると
時の旅気分が味わえます。
場所は、こちら 続きを読む
姿見の池と腰掛石
菅原道真(845年-903年)の伝説
長崎市の中島天満宮に残っている
聖廟記によると
延喜元年(901年)
菅原道真が大宰府に流されたとき
従った三澄左近将監時遠は
年老いて
瓜生野(現在の鳥栖市元町)付近に隠居
時遠は子どもがいなかったため
道真の五子、長寿麿を養子に
もらったそうです。
道真は、長寿麿に会うため
しばしば瓜生野を訪れ
そのとき、腰をおろしたのが
腰掛の石
長寿麿に与えるため
水に映した自分の顔を描いたのが
姿見の池
石碑
鳥栖駅から轟木町の日子神社を目指して
歩いていくと、途中にあります。
JRの高架橋をくぐって、すぐ左
駐車場はないので、
歩いて行きましょう。
線路沿いに歩いていくのも楽しいし
商店街をのんびり歩くのも良いですね。
せっかくなので
長崎街道を、ちょっとだけ
たどってみるのも良いかも
秋葉町の昔の町並みを見ると
時の旅気分が味わえます。
場所は、こちら 続きを読む